七合小の子どもたち
インフルエンザの予防をお願いします









第3学期が始まりましたが、1月5日が“小寒”で1月20日が“大寒”です。小寒は寒さがしだいに厳しくなっていく頃で、大寒は寒さが最も厳しい頃とされています。「寒の入り」を迎え、まさに寒さも最高潮で連日この冬の最低気温を更新しており、寒い日が続いています。寒さとともに空気が乾燥し、インフルエンザが流行する時季でもあります。
今日の、下野新聞にも『インフルエンザ、県内全域で「注意報」今季初、前年より3週間早く』という報道がなされていました。県内のインフルエンザの患者数が12月24~30日の1週間で1医療機関当たり10.72人となり、今季初めて注意報レベルの10人を超えたための注意報の発令とのことです。
本校でも罹患している児童が出てまいりました。感染予防と感染拡大防止のために、次の点についてご配慮ください。
★ 手洗い・うがいを徹底する。
★ 熱・せき・くしゃみ等の症状がある場合は、マスクを着用する。
★ 体調が悪い場合は、無理をして登校させず、医療機関で診察を受ける。
★ 診察の結果、インフルエンザの場合はすみやかに担任まで連絡する。
先日配付しました「ほけんだより」でもインフルエンザについて注意を呼びかけましたのでご参照ください。なお、ホームページ上の『学校からのおたより』をクリックすると、「ほけんだより」の“12月2号”と“1月号”にもインフルエンザの予防法について触れておりますのでご覧ください。
子どもたちも、七小タイムや昼休みでの外遊びの後には、“お茶うがい”や“手洗い”を励行する姿が見られ予防に努めています。また、乾燥気味の部屋の空気の湿度を保つために加湿器を稼働させています。ちなみに、職員室の湿度計は39%を示していました。乾燥気味です。
3学期の委員会活動が始まりました



1月10日(木)の6校時は、5・6年児童の委員会活動がありました。
今回は3学期の委員会活動の第1回目ということで、2学期の反省と3学期の計画などの作成を行いました。
話し合いが終わった委員会はさっそく活動に入り、図書委員会は図書館の本の整理を行ったり、保健・給食委員会は“インフルエンザ”や“感染性胃腸炎”の予防への啓発ポスターを作ったり、放送委員会はお昼の放送などの分担を練り直したり、福祉委員会は福祉施設に送るカレンダー作りの話し合いをしたり、体育委員会は“なわ跳び強調週間”に向けての準備を行っていました。また、飼育・栽培委員会は、屋外に出て花壇のパンジーの水やりをしていました。
3学期も委員長さんを中心に協力しあい委員会活動を通じて、集団の一員としてよりよい学校生活づくりに積極的取り組んでくれることを期待しています。
新体育館で3学期始業式を行いました






1月8日、新体育館「竣工式」の後、引き続いて転入生の紹介と3学期始業式を行いました。
始業式に先立ち、3学期から転入する1年生を全校児童に紹介しました。お互いに元気な「よろしくお願いします」のあいさつが交わされ、全校児童数181名で3学期がスタートしました。
3学期の始業式では、学校長から年の初めの目標や願い・希望をもつことの大切さと、目標に向けての努力を大切にしたいことや、今年の干支の「巳年」「ヘビ」にまつわる話がありました。
また、最も短い学期ですが1年間のまとめの学期として、勉強や運動に全力で取り組み、それぞれの学年で今身に付けるべきことをしっかり身に付け、来年度につなげられるように大きく成長してほしい。特に、6年生にとっては、小学校生活最後の学期となるので、思い出に残る充実した3学期になることを期待したいという話がありました。
最後に、4年・6年生の児童代表からは、3学期の希望として学習や運動、生活などで頑張りたいことが堂々と発表されました。予定していた、2年生の代表児童は、インフルエンザのために出席停止となってしまったので、後日、全校集会の折に発表の機会を設けたいと思います。
始業式の後には、全校児童で「新体育館」と「旧体育館」で記念の集合写真を撮影しました。
新体育館「竣工式」が行われました









1月8日、大谷市長様はじめ多くの来賓の方々をお迎えして、新体育館の「竣工式」を行いました。
昭和48年5月に建築された旧体育館の老朽化・耐震基準未満のため、体育館の全面改築(新築)工事が昨年の5月より着工しており完成が待たれていました。
式典に先立ち、9時から体育館内を見学した後、体育館内に全校児童が入場し、「竣工式」を行いました。
始めに、大野学校教育課長さんから体育館が完成するまでの経過報告がなされました。
大谷市長さんによる式辞や来賓の方を代表して中山市議会議長さんの祝辞をいただいた後、教職員を代表して学校長と6年生の小口さんが児童を代表して「御礼の言葉」を述べて、式典を終わりました。
長らく待ちわびた体育館が完成し、いよいよ体育や諸行事に使用できるときがやってきました。今日の感激を忘れず、体育館を作ってくださった多くの方々の気持ちを考え、愛着をもって大切に使っていきたいと思います。
なお、社会体育では1月21日(月)から使用開始となります。使用上のルールをよく守って、楽しく、有意義に使ってほしいと思います。
明日の、新体育館「竣工式」準備は整いました





新体育館の「竣工式」を明日に控え、今日の午後には、市教委の皆さんが会場設営に見えました。
アリーナの床面を保護するビニールシートも先日搬入され、これからは、体育館で机や椅子を使用するときには、シートを敷くことになります。シートはかなり重いので、巻き取りなどには怪我に十分気を付けて行う必要がありそうです。
教育委員会の皆さん、式場の設営、大変お疲れ様でした。
また、3学期始業式は、竣工式の後に行います。会場は冷え込むことが予想されますので、暖かい服装を準備してください。明日、皆さんに会えることを楽しみにしています。
1月8日(火)始業式の登校時刻及び下校時刻について
※ 登校時刻 通常どおり(8:05)
※ 下校時刻 14:20
スクールバスの運行時刻
早便:学校発・・・14:20(すみれパーマ方面・入滝田方面・大桶方面)
遅便:学校発・・・14:40(集会所北方面・平野中山方面・滝田本郷方面)
2013年1月1日「あけましておめでとうございます」
東京地方の「初日の出」の時刻は、午前6時51分でしたが、七合小学校には7時15分過ぎに市のシンボルマークの様なお天道様が顔を出しました。
新しい年を迎えての夢や願い、期待・希望。今年はどんな目標を立てますか。光輝く年をめざして、まずは健康に気を付けて着実に進んで行きたいものです。
そんな願いを込めて、「ダイヤモンド富士」ならぬ「ダイヤモンド七合」をアップします。





「職員作業」を行いました















12月26日(水)は、全職員での「職員作業」(整頓活動)がありました。今回は午前中に体育小屋と体育館倉庫のテントや体育用具の搬出準備を行い、午後に新体育館の使用説明と引き渡しが行われた後、新しい体育倉庫と体育館倉庫にそれぞれの物品を搬入しました。
ついでに、校長室わきの園芸用の物品収納コーナーも整頓され、お陰様で見違えるようにきれいになりました。
冬晴れで快晴の天候でしたが、北寄りの季節風が強く吹き付ける中での作業でしたので、寒さが身にしみました。
また、校庭では寒風が吹き付ける中、野球場の整備が進められており、マウンドに土が盛られ内野の部分には川砂などを入れて、ローラーをかけていました。
それぞれの場所に各用具は納められましたが、更に使いやすい状態になるように整理整頓に心がけていきたいところです。
先生方、終日の作業で大変だったと思います。お疲れ様でした。
「2学期終業式」は、最後の体育館で行いました






昭和48年4月に統合小学校として授業を開始し、5月には今の体育館が完成したということですので、39年間の歴史の幕を閉じる体育館での2学期終業式となりました。
式では、まず始めに学校長が、今までお世話になった体育館への感謝について触れた後、充実の2学期の振り返りをしました。そして、冬休みを迎えることに際して、注意や新年を迎えることについての心構え等について話し、最後に1月8日の始業式の前に新体育館の「竣工式」も控えていることから、新体育館も皆が元気な姿で登校できることを願っているということで締めくくりました。
児童代表の2学期の反省では、1年 川島さん、3年 髙野さん、5年 岡崎さんが、2学期の反省と今後の抱負を上手に発表してくれました。それぞれに、新しい年を迎え素晴らしい年になることを期待しています。
会場の、椅子の後片付けが終わった後、5年生は体育館に別れを惜しむかのように、全員で集合写真を撮りました。
「すこやか表彰式」が行われました






12月21日(金)に、大谷市長様、岡教育次長様、大金すこやか室長様をお迎えして、「すこやか表彰式」を行いました。今回は、努力賞5名、奉仕賞3名、親切賞3名、体育賞3名、文芸賞2名の合計16名の児童が表彰されました。
一人一人に大谷市長様より表彰状が授与され、岡教育次長様からは記念メダルをかけていただきました。
表彰を受けた児童は、緊張しながらもしっかりと「ありがとうございます」とお礼を口にするなど、礼儀正しく式に臨めました。
表彰の後、市長様からは受賞者へのお祝いの言葉と、全校児童へは冬休みを前にして生活リズムを大切にすること「早寝・早起き・朝ごはん・テレビを止めて外遊び」のスローガンと「新学期には新体育館も皆の登校を待っている」というような励ましの言葉をいただきました。
また、受賞者を代表して、6年の大森君が「地元の和紙でできた表彰状と記念のメダルをいただいたことによる受賞の重みを受け止めて、これからも頑張っていきたい。」と受賞への感謝の気持ちと今後への抱負などについて、児童代表のお礼の言葉として述べました。
受賞された皆さん、本当におめでとうございます。今回の受賞が糧となって、これからも更にすこやかに育つことを願います。
【お知らせ】
12月25日(火)は「2学期終業式」で特別日課となります。
※ 3校時に「終業式」を行った後、「学級活動」を行い、給食後に下校となります。
※ 下校時刻 13:15
スクールバスの運行時刻
早便:学校発・・・13:15(集会所北方面・平野中山方面・滝田本郷方面)
遅便:学校発・・・13:35(すみれパーマ方面・入滝田方面・大桶方面)
2学期「VS(ボランティア清掃)大作戦」を行いました


















12月20日(木)の午後には「VS(ボランティア清掃)大作戦」が行われました。この「VS大作戦」は、福祉委員会の児童が「気づき、考え、実行する」というVS活動の意義を重視し、自分たちで学校のどこに重点を置いて清掃活動に取り組むかというもので、進んで清掃することにより、物を大切にする気持ちや愛校の精神を育てるものです。
冬場は水を使う作業は辛いものがありますが、子どもたちは寒さにも負けず、手を真っ赤にしながら水雑巾をかけたりトイレや流しの排水溝の汚れを一生懸命落としたりしていました。中には、歯ブラシを使ってサッシの桟や流しの細かいところの汚れを落としている児童もいました。
昔から「清掃することは心を磨くこと」と言われてきました。清掃することを通して、気づきが深まり、今まで何気なく見ていた身の周りへの関心が芽生えてきます。また、きれいにすることで汚いところに目が向くようになり、変化に敏感に気づくようになります。そして、心を込めて清掃をすることにより、その場所に対する愛着が湧き、大切に使いたいという気持ちも強まります。是非、こういった活動を通して、子どもたちの愛校心を育んでいきたいと思います。
寒い中、本当にお疲れ様でした。
全校集会「賞状の伝達と表彰」を行いました


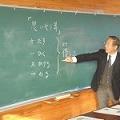
今朝は、全校集会で賞状の伝達と先日の「校内マラソン大会」の表彰を行いました。今回の伝達は、先日伝達した「子どもの人権ポスター原画コンテスト」についての烏山支局からの賞状と「読書感想文コンクール」「児童作品展」「小中学生交通安全ポスターコンクール」「ミルクの国とちぎ小学生絵画コンクール」のものを伝達しました。
また、本日の下野新聞にも掲載されていた「人権の作文コンテスト」の記事から、宇都宮地方法務局長のあいさつのキーワード「いたわり、優しさ、信頼する心」と最近のCMで良く耳にするACジャパンの「思いやり算」についての紹介をして、各学級や友達関係でもお互いに思いやりをもって、優しい心で生活してほしい旨のお話をしました。
「体育館改築工事消火設備点検」が行われました















12月18日(火)10時より、完成間近の新体育館において消防署の立会による消火設備の点検と消防検査が行われました。
特に、工事期間も残り少なくなり、検査と並行して最後の手直しや調整も急ピッチで行われていました。放送設備の調整では、ジャズで有名な“テイク5”を流しながらの調整で良い雰囲気でした。
現在、工事の方はステージ周りの「緞帳」や「各種バトン」の取り付けと、屋外の「玄関・ポーチ」や「渡り廊下」の工事も最後の仕上げに入ってきているようでした。
今日は、外部フェンスや現場事務所も撤去されたため、校庭からも外観が望めるようになりました。
また、バックネットの設置も先日完了し、今までの野球場とは幾分雰囲気が違うものとなりそうです。
「2学期全校児童集会」が行われました









12月19日には、児童会主催による「全校児童集会」が行われました。計画委員のメンバーが代表委員会での話し合い活動をもとに準備を進めてきた、クリスマスを意識した楽しい集会でした。
始めに、6年生がユニークなサンタクロースやトナカイに扮して、ステージで「クリスマスのサンタダンス」を披露してくれましたが、中には、トナカイではなく馬の被り物で登場する委員もいました。クリスマスにはちょっと早いクリスマスプレゼントをもらったようでした。
その後、縦割りの「なかよし班」に分かれてゲームを行いました。ゲームは、「〇×クイズ」と「伝言ゲーム」を行いましたが、上級生のお兄さんお姉さんが下級生の面倒を見ながら和気あいあいの中での集会になりました。
「中山地区道路拡張舗装工事」終了しました









今朝は、昨晩からの小雨も上がり放射冷却も無く、比較的暖かな朝を迎えました。年末の「交通安全県民総ぐるみ運動」期間中で谷浅見交差点にも毎朝地域の交通安全協会の方が立哨指導に当たってくださり、子どもたちの安全な登校を見守ってくれています。大変お世話になります。
かねてより要望していました中山地区の「道路拡張工事」がこの程終了し、側溝に蓋がかけられ歩道もやや広く取ることができました。児童の登下校に安全がプラスされると思います。
また、国道294号線沿いのカーブなどの危険個所(岡本瓦工業周辺・青木畳店周辺)についても、一部ガードレールの設置が予定され、先日、現場確認に立ち会いました。年度内には設置がなされるということです。
今後も、通学路の安全確保のための要望を行うとともに、日々の交通安全への啓発活動も行っていきたいと思います。
関係機関のご協力に感謝いたします。
1年生が「パソコン教室」を行いました









12月17日(月)午前の授業で、前回の11月に引き続き、1年生は情報教育の授業のサポートとして、ユーキャンからインストラクターをお願いして、1・2校時にパソコン操作の基本を学習しました。
今回、2回目ということもありパソコンのマウス操作も上手になり、クリック操作にも慣れてきたので、パソコンでぬり絵に挑戦しました。お絵かきソフトを起動し、“ブラシツール”“色の塗り方や色の変え方”“やり直し”の方法などの「ぬり絵の基本操作」を教えていただくと、子どもたちは作業に没頭していました。中には、お互いに教え合う様子も見られました。マウスを駆使して、思い思いに素敵なカレンダーを作成していました。
「新入生中学校説明会」が行われました



12月14日(金)の午後、新入生と保護者を対象に「中学校説明会」が行われ、6年生は烏山中学校を訪問しました。
まず、説明会に先立ち生徒会役員の先輩方より校舎の案内をしていただきました。中学生は「実力テスト」中ということで授業の様子は参観できなかったものの、4階建ての校舎を案内していただけました。
体育館に戻り、まず堀江校長先生からお話を聞きました。校長先生は、小学校と中学校の違いについて「中学校での服装や学習(教科担任制)の違いや、中学校卒業後は進路の選択を迫られることについて、3年間の中学校生活でこれから自分で進んでいく道(進路)を自分で決めなければならないことが一番の違いです。」とおっしゃっていました。そして、中学校入学前までには、『当たり前のことを当たり前に出来る』基本的な生活習慣をしっかりと身に付けておいてほしいと強調していました。
次に、担当の先生方より「中学校生活全般」「入学までの準備」などについての説明がありました。
また、生徒会の役員からは「生徒会活動」についての説明がありました。
最後に、部活動の説明を各部の代表生徒が緊張の面持ちで説明してくれました。中学校では部活動が非常に大きな位置を占めます。子どもたちにとっても中学校生活を充実させ、豊かな人間性の育成のためにも、自分自身の特性に合った活動を選択して自己実現を図ってもらいたいものです。中には、「郷土芸能部」に興味を示している児童もいました。
今回の説明会によって、中学校への不安が解消できたり、入学後の夢や希望がもてたりできたのではないかと思います。中学校には大変お世話になりました。
「避難訓練Ⅱ」を行いました









12月13日、清掃活動時に避難訓練を行いました。今回は初めての試みで、学級単位ではなく“なかよし班”(縦割り)での避難訓練を実施しました。
先日の夕方、地震がありましたが、いつ・どんな時に地震に遭遇しても安全な行動が取れることを意識させる機会として、今回は、地震を起因とする火災に対する避難訓練を行いました。更に、防災教育も兼ねて、「起震車」を依頼しての実際の地震体験も行いました。
児童に対し、避難時の3要素「無言」「整然」「敏速」を守って避難することに重点をおいていますが、今回は上級生の判断力や適切な誘導の訓練にも視点を当てて実施しました。その結果、上級生がうまく低学年の児童を気遣い安全に誘導する姿が見られました。また、避難場所でも、学年のリーダーが声をかけ、列を整えている様子も見られ安全への意識付けが高められたと思われます。
最後に行った「起震車」の地震体験では、学年に応じて震度を調節していただき、低学年には刺激が少なめの震度3程度の地震で行い、徐々に学年が上がるに従って、実際の「阪神淡路大震災」や「関東大震災」「新潟地震」「宮城県沖地震」などの地震を模擬的に体験しました。そして、体験版ではありませんでしたが、「東日本大震災」と同じ震度7を起こして見せていただきました。その揺れの大きさには改めて地震の恐ろしさを実感しました。貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。
「第2回七合地区青少年健全育成推進会議」が行われました



12月12日(水)の夕方、青少年を育てる会七合地区協議会事業部主催の「第2回七合地区青少年健全育成推進会議」が本校会議室で行われました。
冬休みを間近に控え、本校や烏山中学校から地域に向けての情報発信・連携を目的に「地域の児童生徒の冬休みの過ごし方について」地域の自治会長さんを中心とする会員の皆様にお知らせするとともに情報交換を行いました。
この日は、地元警察官駐在所の仁平所長さんからも、「防犯や地域安全・交通安全について」、最近の犯罪の傾向や手口などについて情報をいただきました。また、参加されている各地域の代表や団体の方からも、それぞれの立場での情報をいただき、「子ども110番の家」の最近の状況等、地域ぐるみで子どもたちを守ろうという強い意気込みが感じられました。
最後に、高橋会長さんからは、1月13日に行われる「市駅伝大会」に向けての参加協力等の呼びかけがありました。
学級紹介-2(1年生・6年生)がありました






12月13日(木)の七小タイムに、児童会集会で学級紹介(1年生・6年生)がありました。1年生は全員で国語科の教材「くじらぐも」の音読発表(暗唱)と自己紹介、最後に「くじらの赤ちゃん」の合唱と鍵盤ハーモニカの合奏を行いました。ステージの上では礼儀正しく礼をしてから自己紹介をする1年生の姿に「立腰」の教えを感じました。
6年生も学級全員で漢詩「春望」などの暗唱と早口言葉の発表を披露しました。早口言葉では、活舌が滑らかで流れるように発表する6年生に拍手が起きたり、またその逆で、笑いを誘うような様子が見られたりして場を和ませてくれました。
それぞれの学年とも、先日の学習発表会で発表したものですが、当日の発表が見られなかった学年がほとんどですので、立派な発表に大きな拍手が送られました。
2年生が「子ども祭り」を行いました












2年生が生活科の時間に「子ども祭り」の計画を立て、体験コーナーの準備やおみやげ(ご褒美)の折り紙作りなどをしてきました。12月13日(木)3・4校時を使い、1年生を招待し「子ども祭り」を実施しました。
屋台村方式で、1年生には「スタンプカード」を発行し、スタンプを押してもらいながら各コーナーを回っていくというやり方をとりました。魚つりコーナー・的当てコーナー・輪投げコーナー・ボウリングコーナーなど楽しい遊びに1年生も大喜びでした。中でも、宝探しコーナーでは、新聞紙の切りくずの中に隠してあるカードを探し回る無邪気な姿には、思わず笑いが出てしまいました。それぞれのコーナーで、得点をゲットし、得点ごとにご褒美がもらえるので、夢中になって挑戦していました。
2年生が、お兄さん・お姉さん役となり、各コーナーの説明や運営などで1年生をもてなす様子が微笑ましく見えました。

